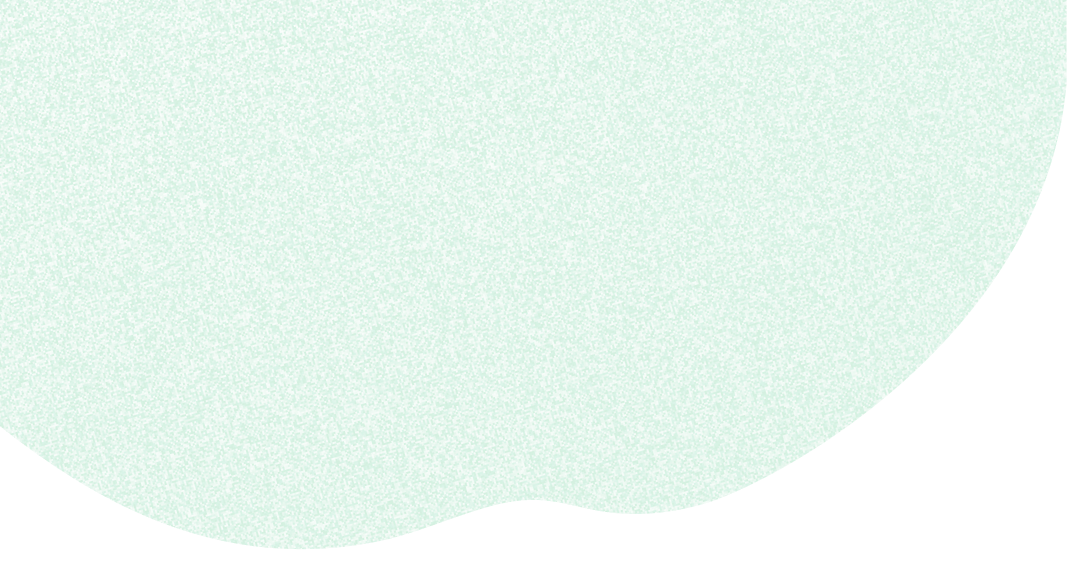IoT研修会の紹介①
第二技術部の鷲崎です。
弊社のHPを刷新することに伴い、新たにコラムのコーナーを開設するとのことで
執筆の機会をいただきましたので、今回は2024年春に開催したIoT研修会について書かせていただこうと思います。
IoT(Internet of Things)とは
Internet of Things(モノのインターネット)
センサー、制御装置、電子機器、車、家電、建物などの様々な「モノ」がインターネットに接続し、相互に情報交換をする仕組み。
(イギリスのケビン・アシュトン氏が1999年に初めて提唱)
なお、「モノ」がネットワークを介して繋がるという概念自体は1980年代から存在している(例:TRONプロジェクト・ ユビキタスコンピューティング…)
目次
- IoT研修会について
- マイコンモジュールの選定
- まとめ
1. IoT研修会について
弊社では年2回、全社員が一同に会しての全体研修会を開催しており、毎回異なるテーマを設けて、社内の有識者もしくは外部講師による研修活動を行っています。
そして、2024年春の研修会の開催にあたって、当時IoTに興味のある社員が(私含め)複数いたことから、研修会のテーマが「IoT入門」に決まり、私が主担当として携わらせていただくこととなりました。
今回の研修では、「IoTとは何か・どんなことができるのか」を実際手を動かしながら体得してもらい、普段の業務ではあまり触れる機会の少ないIoT分野について興味関心を持ってもらえることを目標とし、以下のようなカリキュラムを作成しました。
- イントロダクション:IoTの概説と使用するマイコンモジュール・センサー・開発環境の説明など。
- 演習:講師の説明に沿って、センサーを使った簡単なIoTシステムを作ってみる。
- チーム制作:各チームごとにアイデアを出し合い、センサーを活用したIoTシステムの制作体験を行い最後に発表する。
しかし、実施にあたっては、以下のような課題がありました。
- 研修当日は他のテーマの研修もあるため(後になってから判明した!)、イントロダクションからチーム制作発表まで数時間で終わらせる必要がある。
- 全社員が参加することから、プログラム言語での開発経験やスキルがない人もいることも考慮する。
- 使用するパソコンは各自持ち込みになるため、インストールを伴う環境構築を行わせるには抵抗がある。
それらを踏まえて、今回の研修に最適なマイコンモジュールを選定する必要がありました。
2. マイコンモジュールの選定
いきなり結論から申し上げると、使用するマイコンモジュールにはM5Stack社の「M5Stack Core2 for AWS」を採用しました。

M5Stack公式サイトより引用 https://docs.m5stack.com/ja/core/core2_for_aws
IoT入門の候補としては他にも Raspberry Pi Pico W や Arduino UNO R4 WiFi といったWiFi通信対応マイコンボードがありますが、以下の点でM5Stackが優位であると判断し採用しました。
- バッテリー、LCDをはじめ、マイク、スピーカー、LED等が最初から一体になっており、組み立てや配線といった作業が不要。
- M5Stack向けに用意された豊富なセンサーユニットをケーブルで簡単に接続可能。
- ブラウザ上で動くビジュアルプログラミング環境「UI Flow」が使用可能。
1.については、組み立てや配線にかかる時間を節約できるほか、配線ミス等によるトラブルを回避できることから、特に時間の限られている今回の研修では大きなメリットとなりました。
2.については、M5Stack社がM5Stack向けに各種センサーユニットを販売しており、基本的には本体側のコネクタと付属のケーブルで繋ぐだけで使用可能な状態になるため、慣れていない人でも使いやすく、また接続ミスによるトラブルが防げるメリットもあります。

M5Stack本体と温湿度センサーを接続した様子。いずれも初めからケースに収められており、電子工作に慣れてない人でも手軽に扱える。
3.が今回M5Stackを採用した最大のメリットで、Webブラウザ上で完結しているため追加のインストールや環境構築といった作業が不要。いつも使っているWebブラウザからUI Flowのサイトにアクセスするだけですぐに開発を始められるという、まさに今回のような研修のためにあるかのような開発環境です。また、「UI Flow」はビジュアルプログラミングなので、ブロックを組み合わせていくことでプログラムを作成し、実行できるので、プログラム言語の開発経験がなくてもプログラミングできるという点も今回の研修にマッチしていました。さらに予めM5Stack本体やモジュール、ユニットに対応したブロックが用意されており、とりあえずセンサーを動かしてみようといったことが簡単に実現できるのも、IoT入門者にとっても非常に大きなメリットです。

M5Stackシリーズのビジュアルプログラミング開発環境「UIFlow」。M5Stack本体やモジュール、ユニットに対応したブロックが用意されており、ブラウザ上で操作するだけですぐにプログラムを組んで動かしてみることができる。
あと補足として、M5Stackには様々なマイコンモジュールがあるのですが、その中で「M5Stack Core2 for AWS」を選んだ理由として
- LCDにタッチパネルが搭載されており、UI FlowのUI部品を使って画面上にボタンやスライダを配置できるなどソフト的に入力インタフェースを工夫できる。
- 最初からBottom2モジュール※がついているので、電池容量が大きく、またセンサー接続に使えるコネクタが多い。
- 弊社としてAWSを推しているということ(今回の研修ではAWS IoT Coreは取り上げなかったが今後の展開も踏まえて)
※「Bottom2モジュール」
M5Stack本体の底面に取り付ける、バッテリーと接続コネクタの複合モジュール。このほか様々なモジュールがM5Stack社からリリースされており、それら追加モジュールを重ねて(Stackable)機能を拡張できるのもM5Stackの特徴。
まとめ
全体研修として実施するとなると、時間の制約だけでなく参加者のスキルや経験のバックグラウンドが異なることも考慮する必要があります。さらにマイコンやセンサーを扱うとなると、電気工学の知識や電子工作等の経験がないとどうしても敷居が高いと感じられてしまいますが、今回採用した「M5Stack」と「UI Flow」は、そうした課題をクリアしてくれた素晴らしいプロダクトでした。
次回は実際に研修で行った演習内容の解説と、研修会の様子をお送りしたいと思います。